「この地に生まれた時点で、ハンディキャップ背負ってるって気がしてたんですよね」
自身の出身地についてそう語るのは、作家のこざわたまこさん。彼女が「ハンディキャップだ」と語るその故郷は、福島県南相馬市である。
2011年3月11日の東日本大震災から丸6年が経ち、いよいよ7年目へと突入した今月。
毎年この時期になると震災関係の番組が増え、SNSには「あの日」の振り返り投稿が溢れる。そんなつもりはなくとも、こういった光景がある種の「恒例行事」になってしまっている感も拭いきれない。
そんな空気を遮るようにして今回のインタビューに応えてくれた、こざわさん。2015年に刊行されたデビュー作『負け逃げ』は、故郷である南相馬市を題材にしたというが、そこに描かれていたのは「震災前」の故郷が持つ独特の空気感。
こざわさんが「被災地」になってしまった故郷に感じる正直な思いと、作家として『負け逃げ』に込めた思いに、同じく南相馬出身の筆者が迫る。

こざわたまこ
1986年福島県南相馬市生まれ。専修大学文学部卒。2012年「僕の災い」で第11回「女による女のためのR-18文学賞」読者賞を受賞、デビュー。『負け逃げ』が初めての単行本となる。趣味は演劇鑑賞と漫画を読むこと。好きな作家は重松清、窪美澄。
―― まずはじめに、こざわさんはいつ頃から作家として活動を始めたんですか?
大学を卒業して、企業に勤めながら執筆を続けていました。昔から本をよく読んでいて、高校時代も演劇部で脚本を書いていましたし、大学も文芸創作ゼミを選択しました。
作家として本格的に活動を始めたのは、2012年に『女による女のためのR-18文学賞(新潮社)』をいただいてからですね。その後、出版のお話をいただいて、デビュー作『負け逃げ』の刊行に至りました。
―― 『負け逃げ』は、登場人物が強烈ですよね。毎晩セックスをしに徘徊する女子高生、同僚と不倫し続ける中年教師、引きこもりの兄を持つ不良ぎみの少年……。どうしてこんなに強烈な人々を描こうと?
まず、生きづらそうな人たちを書きたいという思いがあったんです。生活していくうえで感じる生きづらさって、年齢も環境も、言ってしまえば田舎や都会も関係なく普遍的なものだと思ったんです。
例えば、私たちの地元でいう「生きづらさ」を挙げるとしたら、「選択肢」の少なさ。あそこって娯楽施設がほとんどないんですよ。街中にレンタルビデオ屋一軒、コンビニ数軒、みたいな。そんな田舎だから、自然と住んでる人間も保守的になる傾向があると思います。特に、私たちの親より前の世代。
「野口はこの村で一番のヤリマンだ。けれど僕は、野口とセックスしたことがない」 ――衝撃の一文から始まる『負け逃げ』は、2015年に刊行された、作家こざわたまこのデビュー作。
「ど」がつくほどの田舎で営まれる日常生活。その中に確実に漂っている「息苦しさ」。
どこの田舎にも存在するであろう、その独特の空気感を徹底的に描き切っている本作は、著者自身の故郷、福島県南相馬市からインスピレーションを受けている。
「徹底的に描きたかった」と言う著者が描く渾身の田舎物語。キレイごとでは済まされない「リアル」な故郷をご覧あれ。
(新潮社、2015年9月)
―― 本当になにもなかったですよね。私の親も保守的というか、昔ながらの気質で、よく「普通が一番だ」「突拍子もないことするな」って言ってました。大学生の頃、流行っていた赤いパンプスを履いて帰省したら「捨てなさい」って、本気で怒られたり(笑)。
目立つこと、好きじゃないですよね。もし間違って「芸術の道に進みたい」なんて打ち明けたら、「この穀潰しが!」って世界ですし、全く理解されないんですよね。地元で一番“正しい”生き方は、「市役所員か学校の先生、もしくは看護師さん」といった空気が無意識のうちにあるのは確かだと思います。
―― 将来の選択肢も少ない。
そう。だから田舎の中で“なりたいもの”を見つけられない子は出ていく。そうするしかないし、そんな思いで出て行ったら、戻ってくる子も少ないと思います。だってそんな鬱屈とした雰囲気の街、生きづらいじゃないですか。なんていうか、「好きでこの街に生まれたわけじゃないのに、生まれた時点で人生のハンディキャップを背負ってる」……そんな気がしてました。
この物語の人物はみんな、「出て行きたくても行けない」人たち。そんな鬱屈とした空気の中に閉じ込められた「生きづらさ」を、彼らの姿を通して描きたかったんです。
―― もしかすると、そういった「窮屈さ」「逃げられない空気感」みたいなものは、いわゆる「田舎」が共通して持っているもので、『負け逃げ』は、それを代弁しているともいえるかもしれませんね。
田んぼと山と海が南相馬市を形作っている基本要素。こんな絵に描いたような「田舎」が南相馬市である。震災前の人口はおよそ7万2千人。うち65歳以上の高齢者の割合は26%を占めていた。(筆者撮影)〈参考:福島県南相馬市:改定版 南相馬市高齢者総合計画 平成25年2月〉
―― 「被災地」となってしまった故郷・南相馬市に対して、いま感じることはありますか?
「故郷を失うかもしれない」って思ったときに、気づかされたことはあります。これまであんなに冴えなくて閉鎖的だと思っていた地元だけど、「もう元には戻らないかもしれない」と思った瞬間、素直に「やっぱり失いたくない」と感じたんですよね。あんな田舎でも、私にとっては故郷なんだなって。
その思いが『負け逃げ』を書く原動力にもなりました。
―― でも、物語自体は震災の要素を含んでいませんね。どこにでもある田舎の日常が舞台になっている。これにはなにか理由が?
意図的に被災地としての側面は描きませんでした。私にとっての福島は「被災地」ではなかったので。
ただ、震災によって浮き彫りになったことがあるのも確かで、私はそれが「敗北感」だと思っています。震災が起きてから、たくさんの悲しみや怒りがありましたが、それと同時に「諦め」のような気持ちを抱いている自分もいたんです。正直に言うと、「経済的にも貧しくて、文化度も知的レベルも高くない、典型的な“貧しい”私たちの土地。そんな田舎だからこうなったのも仕方ないのかな」って。
なんでそんなふうに感じるのかを突き詰めていったとき、それがもともと土地が持っていた「ぱっとしない感」に起因してると気づいたんです。その「諦め」が、いつの間にか染みついていたんだと思います。
―― 確かに、それが地元の「生きづらさ」の正体かも知れないですね。努力しても行き先のない夢や思い、それらが理解されない空気感、そこから導き出される「どうせやってもしょうがない」っていう諦めの結論。
はい。だからそうやって「うっかり」染み付いてしまった負け犬根性みたいなものを否定したいっていう思いがありました。そうするために震災前の冴えない田舎を徹底的に描き切ってやろうって、そう思ったんです。
―― 地域の「震災後」の姿は多くの人の目に触れるようになりましたが、「震災前」のリアルな姿はそんなに知られてない。「もともとの姿」を徹底して描くことって、地元に生まれ育ったこざわさんだからできることでもありますよね。
そうですね。「被災地」になる前の、ぱっとしない、だけど嫌いになりきることもできない、故郷。
―― 本のタイトル『負け逃げ』も、インパクトがありますよね。これはどんな思いから?
もともと好きな言葉だったんですよ(笑)。でも、これは決して物語に出てくる田舎や、あるいはそこに残った人たちを「負け」と表現してるのではなくて。
逆に言うと「勝ち逃げ」できる人ってごく僅かで、ほとんどの人が大小あれど日々「敗北感」みたいなもの感じて生きてるんじゃないかって。だからネガティヴな意味じゃなく、どんな敗北者にも自分のマウンドから逃げて、せめて「生き延びる」余地くらいは残されていて欲しい、そんな希望を込めて付けました。
―― 今回は地元への思いを執筆につなげていますが、こざわさんが地元と繋がり続けるとしたら、それはやっぱり「書く」ことを通して?
正直、地元とは繋がり続けようとしなくても、嫌でも繋がれていくんだろうなぁと思っています。捨てたくても捨てられないのが故郷だったり、家族だったりすると思うので。「書くこと」を通してっていうのはもちろん今後やっていきたいです。
「故郷から出たい」「逃げたい」っていう人がいる一方で、「地元に住む」という選択をした人たちもいる。だからいつか「故郷に根ざして生活してる人」や「故郷に戻りたい」って思ってる人たちを描けたらなとも思ってます。
それとやっぱり私は、あそこに生まれた人たち、特に若い人たちに見せてあげたい気がするんです。そこに生まれたからって、夢見ちゃいけないわけじゃない。大きな夢語っちゃいけないわけじゃないって。もし誰かが「作家になりたい」と思ったとき、「この街からでも、物書きの人が生まれたんだ」って、そんなふうに思ってもらえて、少しでも後押しできたら……うれしいです。
(インタビューここまで)
東日本大震災を境に、「あの」とカッコ付きで語られることの多くなった被災地。いまでこそ「復興」や「ソーシャル」の旗印を掲げてそのひたむきさが印象的に取り上げられているが、そのどの土地にも震災以前の時間、「被災地前」が存在する。
「ハンディキャップだ」とまで語っていた故郷。だけれど、その田舎が自分の「故郷である」という事実からは逃げられない。
こざわさんの言葉からはそんな現実に対する「諦め」と、だから向き合うしかないという静かな「覚悟」のような熱が感じられた。
レンタルビデオ屋一軒、コンビニ数軒の田舎出身の彼女から、どんな物語が生まれてくるのか。今後が楽しみだ。





















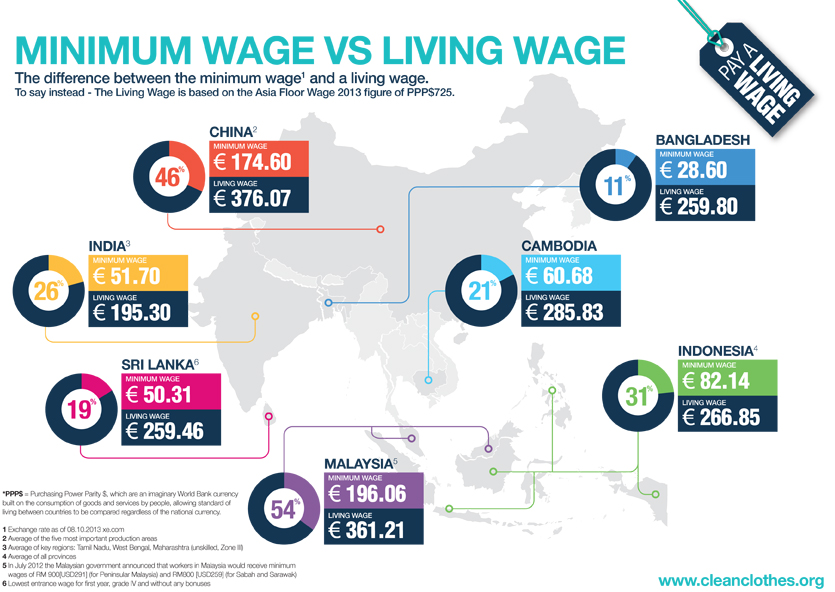

コメントを投稿するにはログインしてください。